- 死亡慰謝料の相場
- 年齢と死亡慰謝料の関係
- 死亡慰謝料は生命の値段ではない
- 相続と死亡慰謝料
- 慰謝料の請求権者
- 内縁の配偶者の死亡慰謝料請求権
- 婚約者に遺族固有の慰謝料は認められるか
- 胎児の死亡と慰謝料について
- 非嫡出子と相続
死亡慰謝料の相場
算定基準
赤い本の基準
弁護士基準では以下のように分類の上、一定の金額が示されておりますが、その金額は一応の目安とされ、柔軟性が維持されています。特別な事情を裁判で立証し、慰謝料が3000万円以上とされる事もあるのです。
| 赤い本 死亡慰謝料 | |
| 一家の支柱 | 2,800万円 |
|---|---|
| 母親・配偶者 | 2,500万円 |
| その他 | 2,000~2,500万円 |
「一家の支柱」とは通常父親や夫を指しますが、経済的な支柱となっていれば、母親や子でも構いません。 祖母や姉等が「母親代わり」として家族を構成している場合は、生活状況によっては「母親」として認めてもよい場合もあるでしょう。 「配偶者」とは夫婦の相手方のことを指しますが、ここでは子がいない主婦や、一家の支柱ではない夫を指すことが多いでしょう。 その他とは、独身の男女、子供、高齢者などを指します。
「親思う心にまさる親心」という吉田松陰の言葉にも表されているとおり、親が子を思う気持ちは大変強いものです。 それなのに一家の支柱(親であることが多いでしょう)が亡くなった場合の慰謝料よりも、 子供が亡くなった場合の慰謝料の方が低いというのは解せないと感じられる方も多いのではないかと思いますが、 一家の支柱の慰謝料が高いのは、単に精神的損害という意味合いだけではなく、遺族の生計維持について配慮されているからであると考えられます。
死亡慰謝料の認定で考慮されるべき事由としては、加害者の態度、事故原因、事故の凄惨さ、唯一の近親者、年齢等が考えられます。
青本の基準
| 青い本 死亡慰謝料 | |
| 一家の支柱の場合 | 2,700~3,100万円 |
|---|---|
| 一家の支柱に準ずる場合 | 2,400~2,700万円 |
| その他の場合 | 2,000~2,500万円 |
任意保険の基準
| 任意保険 死亡慰謝料(例) | |
| 一家の支柱 | 2,000万円 |
|---|---|
| 18歳未満の無職者 | 1,500万円 |
| 高齢者 | 1,450万円 |
| その他 | 1,600万円 |
自賠責保険の基準
遺族分の請求権者は、被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児含む)とします。
| 自賠責保険 死亡慰謝料 | |
| 死亡した本人分 | 400万円 |
|---|---|
| 請求権者1人の場合 | 本人分に550万円を加算 |
| 請求権者2人の場合 | 本人分に650万円を加算 |
| 請求権者3人以上の場合 | 本人分に750万円を加算 |
| 本人に被扶養者がいた場合 | 200万円を加算 |
死亡慰謝料 相場(基準値)の変遷
慰謝料の基準額は物価の動向や判例の傾向など、様々な事情を取り入れて見直されているようです。 基準額の変更は実際は不定期に行われています。この表は金額の変遷を見やすく5年ごとに並べたもので、 実際の変更年とは一致していませんのでご注意ください。参考程度にお考えください。
数字は最低値と最高値を記載しています。自賠責は遺族の人数によって金額が異なるため、1名の場合を最低値にし、3名以上で被扶養者がいる場合を最高値にしています。
| 自賠責保険 | 任意保険(例) | 弁護士会(例) | |
|---|---|---|---|
| 昭和40年ごろ | 150万~250万円 | ||
| 昭和45年ごろ | 150万~250万円 | 300万~400万円 | |
| 昭和50年ごろ | 400万~600万円 | 400万~600万円 | 600万~800万円 |
| 昭和55年ごろ | 500万~800万円 | 500万~800万円 | 700万~1500万円 |
| 昭和60年ごろ | 650万~950万円 | 650万~950万円 | 1100万~2000万円 |
| 平成元年ごろ | 750万~1100万円 | 950万~1250万円 | 1500万~2400万円 |
| 平成5年ごろ | 850万~1200万円 | 1050万~1350万円 | 1700万~2700万円 |
| 平成10年ごろ | 850万~1250万円 | 1100万~1450万円 | 2000万~2800万円 |
| 平成15年ごろ | 900万~1300万円 | 1450万~2000万円 | 2000万~3000万円 |
| 平成20年ごろ | 900万~1300万円 | 1450万~2000万円 | 2000万~3100万円 |
重度後遺障害との比較
一般の方から見ますと、交通事故の慰謝料の中では死亡慰謝料がもっとも高額となると考えられがちですが、実はそうではありません。後遺障害についての慰謝料がもっとも高額になる可能性があるのです。
死亡慰謝料の基準額は2000万円~2800万円程度とされていますが、後遺障害慰謝料は第2級で2370万円、第1級で2800万円(平成21年版赤い本)となっており、死亡慰謝料の金額を超える場合があります。 人の命はもっとも尊いものという考え方からすれば、『命ある限り』、後遺障害慰謝料は、死亡慰謝料に比べれば低額に抑えられるべきとも考えることができます。 しかし単純にその様な考え方だけでは割り切れない事もあるのです。
例えば四肢が完全に麻痺した人は、一生をベッドの上で過ごすことが多くなります。意識ははっきりしているし、家族と会話もできる。『命があってよかった』という気持ちと、 多くの楽しみや、自由を奪われた、『苦しみが長く続く』という気持ちが併存するのではないでしょうか。
両足を失って第1級の後遺障害が残った人のなかでも、リハビリに励み、車椅子で社会復帰を目指すことができる人もいれば、絶望してふさぎ込む人もいます。 身体機能はほぼ正常でも、重度の精神障害が残り、常に看視が必要な状態となる人もいます。
介護が必要なケースでは、家族に重い負担がのしかかることもあります。時にそれが原因で家庭が崩壊する事もあります。
このように被害者の事情は様々ですので、後遺障害慰謝料も被害者ごとの個別の事情を考慮して決めることとなります。 裁判例では、近親者の慰謝料も加算すれば、第1級の後遺障害で、3500万円を超える金額が認められることもあります。 重い障害を背負ったまま生きていくことを余儀なくされることや近親者に与える影響なども考えれば、 死亡慰謝料よりも後遺障害慰謝料を時に高額にするという考え方は理解できると思います。
後遺障害等級認定後の死亡
自賠責保険による後遺障害等級が認定された後に、事故と相当因果関係のある原因で死亡する場合があります。 こういうケースでは後遺障害が残存した苦痛を味わった後に、死亡という別の精神的苦痛を蒙ることとなりますが、 後遺障害慰謝料と死亡慰謝料が別々に認められるケースはまずありません。 しかし後遺障害の認定後、長期間にわたり苦痛の大きい状態で生存したのちに死亡した場合は、慰謝料の斟酌事由として考慮される余地もあるでしょう。
年齢と死亡慰謝料の関係
弁護士会の基準では死亡慰謝料は、『一家の支柱』、『母親・配偶者』、『その他』という分類がされています。この基準を見る限り、被害者の年齢は 慰謝料の金額に反映されていないように思えます。
平均余命を基準に考えた場合に、例えば余命70年あまりの幼児と、平均余命より高い年齢の高齢者とでは慰謝料に違いがあるべきではないのか? そういった疑問は誰しも抱きうるものだと思います。5歳の幼児と80歳の高齢者(配偶者や扶養者のいない場合)は、弁護士会の基準に照らした場合、両者とも『その他』の基準が 適用されることとなりますが、これに違和感を覚える人は多いのではないでしょうか。いのちの価値は平等であっても、それを失うことによって被る 精神的な苦痛は、やはり余命年数の多い者の方が大きいと考えることができると思われます。
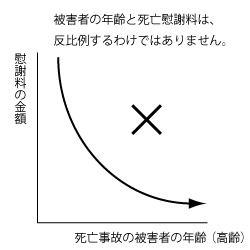
裁判例ではどうか
慰謝料の基準はあくまでもひとつの基準ですので、裁判上ではあらゆる事情が斟酌されて金額が決められます。あらゆる事情の中には 年齢も含まれているはずです。それでは実際の裁判例では死亡時の年齢によって、慰謝料に差がつくというようなことはあるのでしょうか。
そこで『その他』に該当する高齢者と若年者の死亡慰謝料をいくつか比較してみたところ、『年齢を考慮』したというコメントがつく判例は多いものの、 認定額は概ね基準額に近いといえ、余命年数の違いによって慰謝料の金額に大きな違いはないという印象を受けました。 しかし若年者の場合に、基準額より数百万円多く認定しているのではないかと思われる例もいくつか認めることができました。
死亡慰謝料の場合、余命年数が長いことによって、慰謝料が加算される可能性はあるものの、例えば1年でいくらなどの算定方法はなされておらず、あくまでも 一つの事情として扱われるに過ぎないようです。下に弊事務所で集計した裁定例の、死亡慰謝料と被害者の年齢の関係の散布図を掲載します。
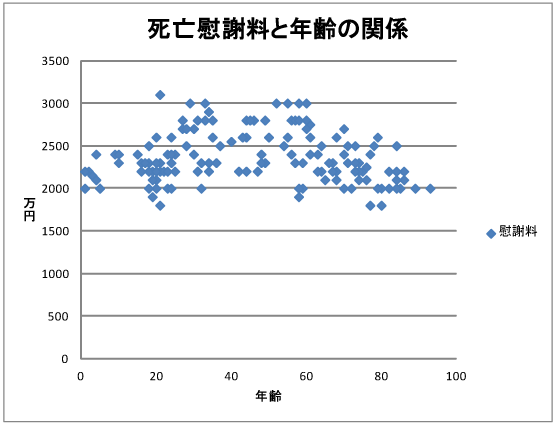
死亡慰謝料は生命の値段ではない
死亡慰謝料算定基準では、亡くなった方とご家族の身分関係によってのみ金額が分けられています。 一家の支柱、配偶者、独身者といった分類です。社会的身分や名声などによる分類はされておりませんので、 大会社の社長であっても、失業中の人であっても、同じ一家の支柱と分類されるのであれば、死亡慰謝料の金額は同じになります。 学歴や職業などの社会的身分関係により死亡慰謝料額を決めるのは、万人に等しく与えられた生命に軽重をつけることになりますので妥当ではありません。
しかしあらゆる身分関係を一切廃して、すべての人間の慰謝料金額を全く同じにすることは、かえって不合理な結果を生むことになります。例えば6人家族の一家の支柱と、 天涯孤独の老人の慰謝料が同じで妥当といえるでしょうか。本人分の慰謝料は同じにして、家族がそれぞれ固有の慰謝料請求権を行使すればいいという考え方もできますが、 そうした個別の事情を基準に組み込んでいくことは、基準の複雑化・適用硬直化を招くことにもなるでしょう。そうしたことも考えますと、 家族という身分関係をベースに最小限の基準付けをしている現在のやり方は、基準の運用の柔軟性も確保されているという面からは、優れたものといえるのではないでしょうか。
『慰謝料の基準額=生命の値段』ではありません。もしも死亡慰謝料の金額が、単純に生命の値段を表すものであれば、 2000万円や3000万円のお金で解決できるようなことではないでしょう。慰謝料は、悲しみを癒すための、ひとつの方法に過ぎないのです。
相続と死亡慰謝料
死亡慰謝料は相続財産か
死亡事故が起きると、亡くなった方に相続が開始します。相続とは被相続人(亡くなった方)の財産が、相続人に移転することです。生前の貯蓄や借金とか、 不動産などはもちろん、交通事故の損害賠償金も相続の対象となります。
死亡事故の場合の損害賠償金の費目の主なものは、死亡までの治療費や慰謝料、葬儀費、死亡逸失利益、死亡慰謝料です。治療費は通常病院に支払われ、葬儀費は費用を負担した者に 支払われることが多いでしょう。逸失利益は法定相続分にしたがって分配されることが多いのではないでしょうか。
慰謝料も法定相続にしたがって分けられることが多いと思いますが、慰謝料はその全てが相続財産というわけではないために、若干注意が必要です。 民法711条に遺族の慰謝料請求権の規定がありますが、これは法定相続人に限定されているわけではありません。被害者に妻と子がいる場合、法定相続人は 妻と子ですが、親がいる場合には、法定相続人ではない親にも慰謝料請求権があるのです。
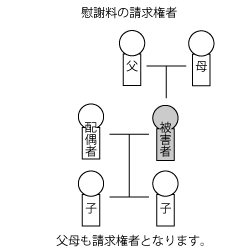
こういう場合、誰に慰謝料の何割を分配するということは決まっておりません。基準といえるものもない状態です。 それでも一般的には、子>配偶者>親という配分が多くなるように思われます。総額が2500万円であれば、子が1300万、配偶者が1000万、 親が200万などという事もあるでしょうし、子が1500万、配偶者が700万、親が300万という事もあるでしょう。 遺族の間で慰謝料の分配方法について話がまとまる場合は それに従えば良い事ですが、話し合いがまとまらない場合は専門家に相談して裁判例などを参考にして再度話し合うか、または調停などの 手続を踏むしかなくなってきます。その際は、同居の有無とか、被害者への依存度(親であれば介護で依存していたなど)などが考慮されることになるでしょう。
相続で一旦争いが起きると、どんなに説得力のある説明をしても、感情が障害となり、相手が首を縦に振ってくれないというようなことにもなりかねません。 そうなる前に、初めから客観的な資料を揃えて話し合いにのぞむことにより、紛争の予防が可能なケースは多いと思います。 行政書士は紛争の相手方と交渉をすることはできませんが、紛争予防のための資料作りをする事ができます。このようなケースでは早めにご相談 いただくと、お役に立てることが多いです。
法定相続分
法定相続分とは、相続人間で争いが起きないように、あらかじめ民法で定めてある遺産の分配の割合です。相続人の組み合わせごとに割合が決められています。
- 【1】配偶者と子が相続人のとき
配偶者が二分の一、子が二分の一ずつ分配します。配偶者と子A,子B、子Cが相続人の場合は、配偶者が二分の一、子A、B、Cがそれぞれ六分の一ずつとなります。 - 【2】配偶者と父母が相続人のとき
配偶者が三分の二、父母が三分の一ずつ分配します。配偶者と父と母が相続人の場合は、配偶者が三分の二、父が六分の一、母が六分の一ずつとなります。 - 【3】配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一ずつとなります。配偶者と兄と弟が相続人の場合は、配偶者が四分の三、兄が八分の一、弟が八分の一ずつとなります。 - 【4】子Aと子Bが相続人のとき
AとBが二分の一ずつ取得します。 - 【5】母親のみが相続人のとき
母親が全部取得します。 - 【6】兄と弟が相続人のとき
兄と弟が二分の一ずつ取得します。
※配偶者は常に相続人となりますが、他のものは先順位の相続人がいると、相続人にはなりません。順位は「子」→「親」→「兄弟姉妹」の順です。 言い換えますと、子と親と兄弟がいる場合は、相続人となるのは子のみです。
遺産は必ずしも法定相続分に従って分ける必要はありません。遺言があればそれに従いますし、ない場合でも相続人間で合意ができれば自由に分割できます。 例えば配偶者と子と親がいる場合に、三者で三分の一ずつ分配することもできます。ただしこの場合は親は相続人ではありませんので、 「相続」ではなく相続人から「贈与」を受けるということになるでしょう。
遺族の人数と死亡慰謝料の関係
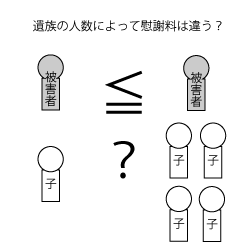
死亡慰謝料は、被害者本人の精神的損害に対する慰謝料と、その近親者が被害者の死亡により受けた精神的損害に対して請求できる固有の慰謝料に 分けて考えることができます。本人に認められる慰謝料は、一旦は本人に帰属したあと相続されるという考え方が一般的です。 これに対して近親者固有の慰謝料は、肉親を亡くしたものの悲しみを慰謝するという意味合いが中心となりますので、相続構成はとらず、遺族本人に直接帰属するものと考えられています。
遺族一人あたりが請求できる金額は、被害者との関係の濃さなどの事情から個別に決めるのが妥当と思われますが、遺族の人数によって金額の算定には影響があるのでしょうか。 近親者に固有に認められる慰謝料であれば、たとえば近親者が一人なら100万円、5人なら各々に100万円ずつ、 総額で500万円とするのが公平と考えられますが、実際のところはどうなっているのか裁判例を調べてみました。
近親者固有の慰謝料が認められた例
- ▼ 事例・判例
- □ 57歳男子の死亡事故で、本人分2600万円、妻と子に100万円ずつ、合計2800万円を認めた。
- □ 48歳男子の死亡事故で、本人分2800万円、妻に200万円、合計3000万円を認めた。
- □ 45歳男子の死亡事故で、本人分2500万円、妻に200万円、母に100万円、合計2800万円を認めた。
- □ 57歳男子の死亡事故で、本人分1200万円、妻に700万円、3人の子に300万円ずつ、合計2800万円を認めた。
- □ 69歳男子の死亡事故で、本人分2200万円、妻に400万円、3人の子に100万円ずつ、合計2900万円を認めた。
いくつかの裁判例を探してみましたが、固有の慰謝料請求権を持つものの人数にかかわらず、 死亡慰謝料として支払われる総額はほぼ変わらない認定がされています。つまり悲しむ遺族が一人の時も十人の時も、支払われる賠償金は変わらないという事です。 精神的苦痛は人数が多ければそれだけ多くなって当然と思いますが、現状ではそのような取り扱いはされていないようです。 因みに赤い本では「基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者とそれに準ずる者の分も含まれている」、 青本では「基準額は、死亡被害者の近親者固有慰謝料もあわせた、死亡被害者一人あたりの合計額である」と説明されています。
遠縁の相続人
相続というと多くの場合、配偶者と子、または親が相続人になります。しかし中にはそれらの相続人が存在せず、法定相続人が兄弟のみであったり、甥、姪のみで あったりするケースが存在します。甥や姪が相続するとなると、被相続人と生前に生活を共にしていたというようなことはまれで、何十年もあったことがないというような ことも多いです。そのような相続人にもやはり慰謝料の相続権はあるのでしょうか。
死亡慰謝料は死亡した被害者本人に対する慰謝料と、遺族に対する慰謝料とに分けて考える事ができます。 このうち被害者本人分の慰謝料は、主に被害者自身の精神的苦痛の軽重により算定されるべきものです。 例えば死に際しての苦痛の大きさ、無念の度合い、加害者の悪質性、扶養家族の有無などの事情が考慮されます。そのようにして計算された被害者本人分の慰謝料は遺族が相続しますので、 たとえ相続人が疎遠であっても、それが金額に影響を与える事はないはずです。
被害者が死亡したことにより、遺族も精神的損害を被ると考えられています。 これは民法第711条の「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」 という規定に基づく考え方です。この考え方は条文に記載されている「父母、配偶者、子」に限らず、それと同じような繋がりのあるものにも慰謝料請求権を認めています。 しかし遠い血縁関係にあるというだけで、交流のなかったものには認められていません。以上のことからすると、遠縁のものでも被害者本人分の慰謝料については通常とおり 相続により取得することができますが、民法第711条による慰謝料は取得できないということになります。
ところが死亡慰謝料の算定基準においては、被害者本人の慰謝料の金額と遺族に認められる慰謝料の金額を格別に基準化することなく金額が示されています。 自賠責保険では死亡慰謝料の計算基準は、本人分と遺族分とに分けて明確に計算するようになっていますが、 一般の損害賠償における計算で、それをそのまま採用することには無理があるように思えます。そのため客観的に遺族の慰謝料がいくらなのかを算定するのは簡単ではありません。 裁判例では本人分のみとして認めるもの、本人分と遺族分を合わせた金額を示して認めるもの、本人分と遺族分の金額を個別に明確にして認めるものが混在しています。 結局のところ遠縁の遺族しかいない被害者の死亡慰謝料の計算は、明確な基準が存在しない以上、本人分と遺族分の金額を明確にしている判例を参考にして、被害者と遺族との距離などを 考慮しつつ考えていくしかないものと思われます。
- ▼ 事例・判例
- □ 67歳男子の死亡事故で、相続人が35年間音信不通だった弟と、面識のなかった姪であった場合に、 死亡慰謝料が1800万円認められた事例。
- □ 76歳男子の死亡事故で、唯一の相続人が交流もなかった母の養子であった場合に、 死亡慰謝料が1700万円認められた事例。
判例は遠縁であるがゆえに慰謝料の請求はできないというような判断はしていません。ただし、金額については遺族固有の慰謝料請求権については認めにくいケースが 多いことからか、相場より若干低めに認定されているという印象を受けます。
相続人が存在しない場合
相続人が存在しないか、もしくは不明である場合でも、相続財産管理人が選任されて死亡した被害者の損害賠償請求が行われる場合があります。 そのような場合でも慰謝料は認められています。 身内といえる人が内縁の妻のみである場合などに、裁判所で特別縁故者として認められれば、財産を分与される可能性もあるのです。
慰謝料の請求権者
近親者の死亡慰謝料請求権
事故で怪我をしたり死亡した場合は、被害者本人だけでなく、多かれ少なかれ近親者も心を痛めるのが普通です。そうした近親者にも慰謝料が認められる余地はあるのでしょうか。 あるとすれば、どのような場合に認められるのでしょうか。
民法の規定
民法第711条では『他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、 損害の賠償をしなければならない。』と規定されています。これをそのまま読み取れば、死亡事故に限って被害者の父母、配偶者及び子のみが 慰謝料請求権を有するということになりますが、実際には次のように解釈されています。
(1)『他人の生命を侵害した』について
死亡という結果に限らず、それに比肩するような精神上の苦痛を受けたと認められる場合は、 近親者は固有の慰謝料請求権を有すると解されています。
- ▼ 事例・判例
- □ 7歳男児が右眼失明、左眼視力0.06、両耳難聴、歩行障害の後遺症を残したケースで、 両親に固有の慰謝料が認められた。(最高裁昭和45年7月16日判決)
(2)『被害者の父母、配偶者及び子に対して』について
必ずしも条文のとおり限定的に解釈されるものではなく、これらの者と同視しうる関係にある者も固有の慰謝料請求権を有すると解されています。 親代わりとして被害者の世話をしていた祖父母や兄姉などが例として考えられます。
- ▼ 事例・判例
- □ 不法行為による生命侵害があった場合、被害者の父母、配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうることは、民法711条が明文をもって 認めるところであるが、右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であっても、 被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、 同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうるものと解するのが、相当である(最高裁昭和49年12月17日判決)
因みにこれにより近親者固有の慰謝料が認められる場合であっても、 赤い本では「基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者とそれに準ずる者の分も含まれている」、 青本では「基準額は、死亡被害者の近親者固有慰謝料もあわせた、死亡被害者一人あたりの合計額である」と説明されていますので、 単純に慰謝料の金額が増えるわけではありません。
事故以前の身分関係の変動は、請求権に影響を与えるか
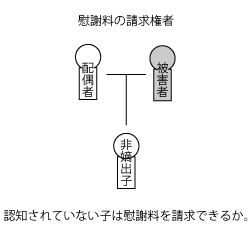
- □ 何らかの理由により戸籍上は離婚していたが、実体上は夫婦生活が維持されていたというような場合。
- □ 籍は入っていたが、事故時には婚姻生活は破綻しており、離婚が確実であった場合。
- □ 共に生活していたが、いまだ認知されていなかった場合。
- □ 養子が亡くなった場合の、養親、実親の固有の慰謝料請求権はどうなるか。
上記のようなケースでは、一律に判断することは難しく、個別に検討することが必要です。 例えば認知していない子と生活を共にしていた夫が、その子を失った場合は、扶養状況や生活状況から通常の親子関係程度の愛情が認められれば、固有の慰謝料請求権が 認められるかもしれませんし、ただ一緒に住んでいるだけで、経済的にも精神的にもつながりが薄いと判断されれば、固有の慰謝料請求権は認められないという場合もあるのではないかと思います。
内縁の配偶者の死亡慰謝料請求権
死亡した被害者の内縁配偶者にも、慰謝料請求権が発生する場合があると考えられています。
法律婚配偶者の場合は、固有の慰謝料請求権のほか、被害者本人の死亡慰謝料を相続するという構成がとられますが、内縁配偶者の 場合には相続権がありませんので、固有の慰謝料請求権のみを持つということになります。また、固有の慰謝料請求権も必ず 認められるものではなく、夫婦生活の実態等を考慮して請求権の有無が判断されることになるでしょう。
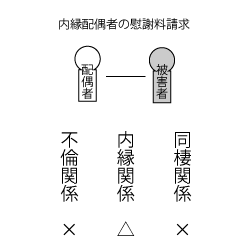
内縁か同棲か
内縁の実態は、平均的な法律婚夫婦の生活に近いものが求められることとなるでしょう。一時的な同棲や、不倫関係の相手方と生活を共にしていたというような 状況では、内縁関係と認められることはないと思います。ただし、配偶者が長年に渡り行方不明になっているなどの事情で、 離婚手続きをしていなかったために、重婚的な内縁関係に陥っていた場合など、特別の事情がある場合は、法的保護に値する内縁と認定される余地もあるでしょう。
扶養利益の喪失
被害者に扶養されていた内縁配偶者は、その利益を失ったことに対する損害賠償請求権も有すると考えられます。 これも慰謝料と同様に当然に認められるものではなく、扶養されていたか否か、また、その程度などにより判断されるべきことです。 この扶養利益というものは、法律婚の場合は逸失利益を相続するという形で遺族に分配されることとなりますが、事実婚の場合は、相続権が 認められないために、扶養利益の喪失という形で、損害賠償請求を認めようとするものです。
- ▼ 事例・判例
- □ 自賠法第72条(政府保障事業)の請求において、死亡被害者の内縁配偶者は、将来の扶養利益の喪失を損害として賠償請求することができる。 政府が内縁配偶者に扶養利益の喪失に相当する額を支払った時は、その額は相続人に填補すべき死亡被害者の逸失利益の額から控除すべきであるとした事例。
婚約者に遺族固有の慰謝料は認められるか
婚約は婚姻の予約であって、当事者相互間では将来婚姻を成立させる義務を負うことになりますが、 婚姻成立までは身分関係に変動はありません。法的に保護される身分関係がない場合にも、711条を 類推適用して、固有の慰謝料を認める余地はあるのでしょうか。
同視しうる身分関係とは
上で説明した最高裁昭和49年12月17日判決でいう「同視しうる身分関係」というのは、具体的には何を指すのでしょうか。 婚姻や養子縁組などの法的な枠組みが重要なのか、あるいは実際の生活状況を重視するのでしょうか。 類推適用を受けた例としては、祖母、未認知の子の父親、内縁の妻などがあります。 内縁の配偶者や認知されていない子の父親の場合、法律上保護される身分関係はありません。そうすると判例の「実質的に 同視しうる」という文言からしても、法的な関係があることが711条類推適用の要件となるわけではないと考えられます。
しかしだからといって、固有の慰謝料は容易に認められるわけではありません。認められる余地はあると思われますが、単に婚約をしていたというだけではなく、 たとえば婚約前または後に、夫婦生活と同視できるような共同生活を長く続けていたなどの、実体的な要件も必要となるでしょう。
たとえ結婚式の日取りまで決まっていた場合でも、本人の慰謝料斟酌事由とはなり得るものの、 婚約者の固有の慰謝料として認められるのは、現状では難しいことが多いのではないでしょうか。
胎児の死亡と慰謝料について
胎児の権利
今の法律の枠組みで胎児の死亡損害を考えたると、民法では私権の享有は出生に始まるとされているため、死亡した胎児自身には損害賠償請求権がありません。 そのためは一般の死亡慰謝料基準が使用されることなく、妊婦や夫の慰謝料として論じられ、低額に算定される傾向にあります。
出生という境界
胎児が死亡した場合には、逸失利益も請求できません。ただし早産後に死亡した場合などは認められるケースもあるようです。 法律上、胎児と人を区別する意義はあると思いますが、生命は出生に始まるものではありません。 不法行為による生命侵害の場合に、結果として出生を境に、これほどまでに損害賠償額に差異ができることは、妥当とはいえないのではないでしょうか。
そもそも出生にはどういう意味があるのでしょうか。通常37~41週くらいを正期産といいますが、それよりはるかに早く出生する場合もあります。 現在は医学の進歩により、早産した超未熟児であっても、生命を維持することが可能となってきています。例えば25週くらいで出生した子と、 同じ25週でも母体内にとどまる胎児について、何が違うというのでしょう。
母体保護法の規定
一方で我が国の法律では、一定の要件のもと、経済的理由等による妊娠中絶を容認しています。 これは見方によっては、中絶が許される妊娠週数内の胎児の生命を、それ以上の場合と区別しているものと捉えることができます。 どこかで線を引かなければならないとすれば、損害賠償を考える上でのボーダーラインとしても、機能させることができるのではないでしょうか。 合理性だけで解決できる問題ではありませんが、少なくとも出生という境界よりは、妥当な解決を導きやすいのではないかと思います。
私は、『出生前であっても、一定の妊娠週数を経た胎児については、近い将来出生する高い蓋然性が認められるので、出生後の乳児と同様の損害の算定を行う』 という考え方が広まってもいいのではないかと思います。
成長の度合いによって金額をかえることは妥当なのか
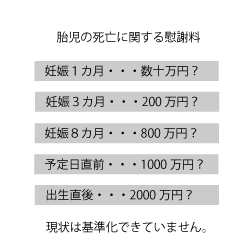
胎児を流産や死産した場合の慰謝料は、現在のところ明確には基準化されていません。ただし、大体の目安として、出生後の新生児よりは低く算定され、 その金額は母胎内での成長の度合いによって変わってくるという傾向があるようです。例えば妊娠3ヶ月では200万円、10ヶ月では800万円といった具合です。
しかし、上記のような考え方が判例の傾向だとすれば、個人的には大きな疑問を感じます。例えば出産予定日1日前の胎児が死産した場合の慰謝料は新生児と差がつけられるのでしょうか。 法的な考え方からは差をつけることができるとしても、一般常識的にはつけられないのではないかと考えられますが、 差がつけられないのであれば、予定日1ヶ月前の胎児が死産した場合とはどうでしょうか。 前述のように母胎内での成長の度合いによって慰謝料の額を割合的に計算するという取り扱いがなされるのであれば、 新生児の10分の9の金額が目安となるのでしょうか。妊娠5ヶ月の胎児であれば、新生児の10分の5の金額が目安となるのでしょうか。
妊娠週数で差をつけるべきではない
両親にとっては10ヶ月の胎児を失うのも、5ヶ月の胎児を失うのも大きな違いはないように思います。これから生まれてくる命を失う悲しみについて、 わずかな時間の違いから、何百万円もの慰謝料の差をつけて評価してしまうというのは強い疑問を感じずにいられません。 特に母親は生涯悲しみを背負っていくことになるのですから。
答えを出すのは難しい問題ですが、ある一定以上の期間(例えば胎盤の完成など)を越えて成長している胎児の場合は、同じような金額を 基準に算定できるようにした方が、親の気持ちに近い考え方ではないかと思います。胎児の死亡について慰謝料の基準化が進まないのはそれなりの理由があってのことだと思われますが、 紛争予防という観点からも、赤い本などでの基準化が待たれるところです。
非嫡出子と相続
非嫡出子とは (※平成25年9月4日最高裁大法廷で第900条4項は違憲と判断されました。それにより非嫡出子の相続差別は是正されることとなります。 この記事の内容は過去のものとなりますが、参考のためにしばらく残しておきます。)
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことを嫡出子といい、 それ以外の内縁関係の男女や婚姻関係のない男女の間に生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子)といいます。
民法第900条4項では、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とされています。つまり、嫡出子と非嫡出子が二人で3000万円を法定相続分に したがって相続する場合、嫡出子は2000万円、非嫡出子は1000万円を相続するということになるのです。
第900条4項の合憲性について
この規定は憲法14条(法の下の平等)に反するのではないかという考え方があり、それを肯定する判断が裁判所で示されたこともあります。 しかし現在のところ、最高裁判所の決定(平成7年7月5日)により、民法第900条4項は違憲ではないと判断されています。法定相続分を定めた規定は、遺言による 相続分の指定がない場合などに、補充的に機能する規定でしかないこと、法律婚を保護する必要があることなどが、主な理由とされているようです。 最高裁平成21年9月30日決定においても同様の結論がだされました。
分配方法
裁判上、死亡慰謝料の請求の仕方としては、次の三つの方法があります。第一に、死亡者本人の慰謝料のみを請求する方法、第二に、本人の慰謝料と近親者固有の慰謝料の双方を請求する方法、 第三に近親者固有の慰謝料のみを請求する方法です。
死亡事故の被害者Xの相続人および慰謝料請求権者が、嫡出子Aと非嫡出子Bの二名である場合に、第一の方法で3000万円の慰謝料を請求すれば、Aが2000万、Bが1000万と分配することになります。 反対に、第三の方法で請求すると、特別な事情のない限り、AもBも1500万ずつ分認められることになるでしょう。 死亡事故による損害は慰謝料だけではなく、逸失利益などもあります。例えばAは独立して生活していたが、BはXに現に扶養されていたという場合はどうでしょうか。AB間で分配方法について合意ができず、 法定相続に従った場合、相続財産がAの方に多く分配されるのは、Xの望むところではないことが多いでしょう。 遺言などで事前に対策を立てておけば良いといっても、事故死という出来事までを予測して遺言を残すことを求めるのは、酷としか言い様がありません。
残念ながら、嫡出子と非嫡出子の間に争いのある、死亡慰謝料請求に関する裁判例は見つけることができませんでしたが、 個別の事情により非嫡出子の相続分が制限されるのが著しく不当といえるような場合には、近親者固有の慰謝料を非嫡出子に有利に配分するなどの措置が望まれます。
